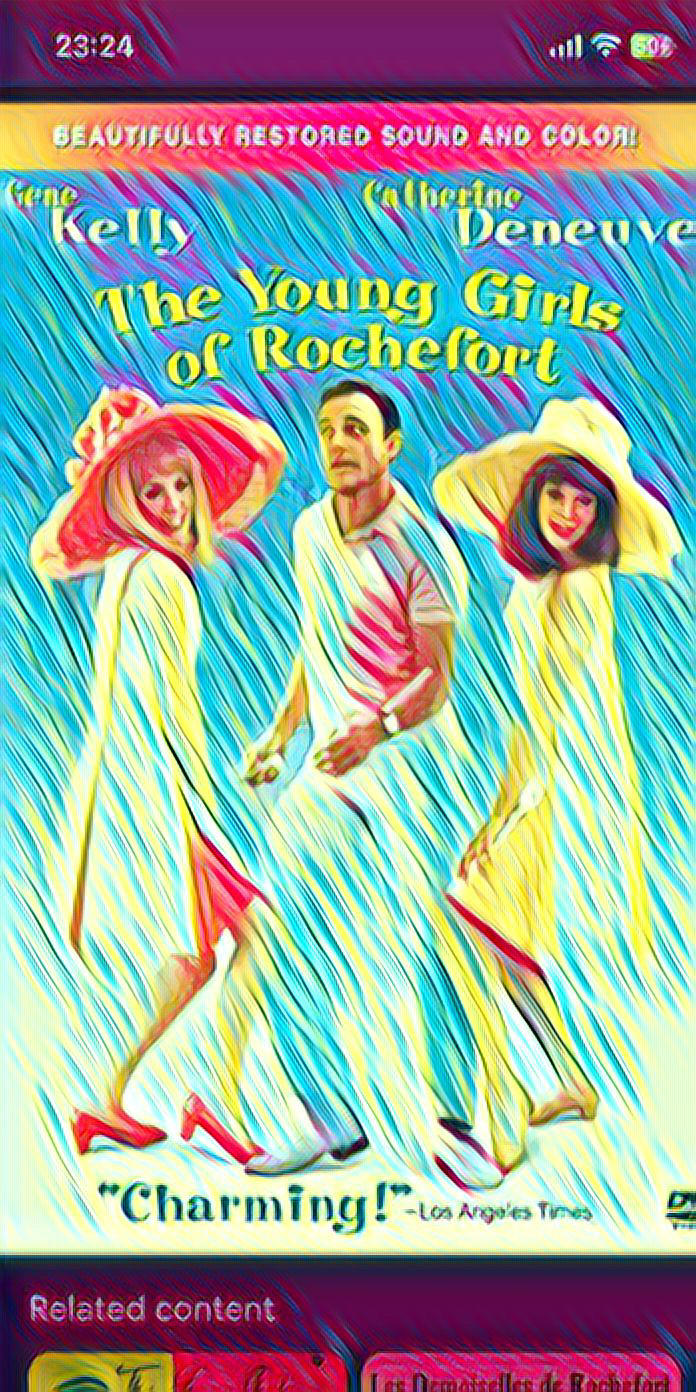『杖と翼』木原敏江 革命という大義に反する者は粛清すべきという行き過ぎた理想主義者を描いた : 9点
松田遼司の「旅行・音楽・美術好きのための映画・漫画評論」。現代でも通用する過去の名作を中心にお届けします。
漫画評論の第4回目は、世の中に平等を実現する革命の大義に反対する者は全員粛清すべきという実在の理想主義者と彼のその純粋な信念をも曲げてしまう自己犠牲による他者への愛を目指す聖女という二人の生き様をフランス革命を背景に描いた名作木原敏江『杖と翼』を紹介します。
『杖と翼』の概要
『杖と翼』は、『夢の碑』などの幻想的な歴史作品で知られる木原敏江先生による隠れた名作歴史恋愛漫画です。筆者はほとんどの作品を保有していますが、木原敏江先生というと『アンジェリク』などを除くと日本を舞台にした作品が多いのですが、この作品ではフランス革命が舞台となっています。実在した「恐怖の大天使」と呼ばれた美貌の天才革命家のサン=ジュストと彼の初恋であった女性がモデルと思われる聖女アデルの恋と生き様が描かれています。
「杖と翼」とは英語では「wands and wings」です。ハリー・ポッターでおなじみの魔法使いが使う「杖」と天使が持つ「翼」は妖精や聖女を表しています。実は主人公はサン=ジュストではなくアデルということでしょうか?
バスチーユ襲撃から革命普及を恐れる列国との戦争、貧困の中での民衆の暴動とルイ16世一家のベルサイユからパリへの拉致、国王一家の逃亡計画の失敗による王への尊敬が失われる、ブルジョワの味方だった主戦派で立憲王政派のジロンド党の敗戦による権力失遂、国王・王妃・ジロンド派の処刑に始まる恐怖政治、ジャコバン派内での権力争いとテルミドールのクーデターによるロベスピエール派の駆逐によろ恐怖政治の終焉まで史実に忠実に物語が進行していきます。「ベルばら」同様にフランス革命の教科書としても適しています。
そして史上初めて自由と平等、人民主権、三権分立など現在まで引き継がれている民主主義の原則を謳った人民と市民の権利宣言が立憲主義的だったため修正し平等主義を謳った1793年の修正宣言を起草したのがサン=ジュストであり、彼が単なる殺戮者ではなく真の平等を目指した革命家だったことも理解できるでしょう。日本の歴史の教科書では「恐怖政治」は悪として書かれており、ロベスピエールやサン=ジュストは大悪人として教えられます。しかし、二人共清貧を貫き、革命の成功による人民の平等のみを考えていたという点は評価されるべきです。人気漫画・アニメ『キングダム』では始皇帝となる嬴政が「世の中から戦争をなくすために国境をなくす」と宣言し視聴者の心を掴んでいますが、その実現のためには六ヵ国への征服戦争が必要なわけで、敵をすべてギロチンに送った恐怖政治とどう違うのかという考え方もあるでしょう。
革命などの大義の前では恋愛などは小事だというのが小説や映画・漫画などで主流の中で、サン=ジュストがアデルを守ろうと奮闘する姿に感動を覚えるでしょう。そして『杖と翼』というタイトルを象徴すると思われるアデルが持つ「癒やしの力」はファンタジー作品ではおなじみです。しかしこの神秘的な力を愛するものや味方のために使うのではなく、見知らぬ他人や動物のために使うという点が聖女を想起させます。舞台となったフランスだけでなく聖女を崇めてきたカソリックを信仰する国々の方におすすめしたい作品です。
『杖と翼』のネタバレなしの途中までのストーリー
『杖と翼』は、パリの北東100キロにあるソワソンで始まる。名家に生まれ美貌と優秀な頭脳、体力まですべてを兼ね備えた18歳の青年レオン(サン=ジュスト)は、何でも簡単にできてしまうために生きる喜びを見いだせず問題ばかりを起こしていた。静養のために訪れたパリ近郊のオワーズの知人宅でレオンはおてんばで聡明な少女アデルと出会う。彼女が死んだ小鳥を生き返らせるのを目撃したが手品だと思うほどに精神が病んでいた。
オワーズでは、畑を荒らす鹿は貴族の狩猟のためのもので殺すことができず徹夜で追い払いながらの奉公生活を強いられるなど農民は苦しみ、遂に一匹の鹿を殺した男が捕らえられる。そんな悪法は撤廃されるべきだと語る貴族の女性が、アデルの母親クレールだった。特権階級の高僧や貴族が税金を免除され、平民が貧困に苦しのはおかしいというルソーやヴォルテールによる啓蒙思想が当時広まっていた。翌日道端で倒れていた農民を家まで連れていったレオンは、彼が重税にあえぎ借金が増えるためと医師を呼ぶのを断り死ぬのを目の当たりにする。重税にあえぐ農民たちのために本を書いていたというクレールの亡くなった夫と容貌や雰囲気が似ていたレオンはクレールに、「自分ならもっと断固たる態度を取る」と答える。さらにコンピエーヌでの貴族の横暴を目にしたレオンは、遂に革命家という人生の目標を見出す。一方、財産がなくなりドイツの男爵家に嫁ぐことになった母親とともに旅立つ前に、アデルはレオンに求婚し、婚約の証としての指輪を受け取った。
1789年、ランス大学で弁護士だったロベスピエールと法学部生のレオンが出会った。「この国から貧しい人を無くしたい」と演説するロベスピエールにレオンは全面的に賛成で協力すると申し出る。
ドイツのネカー男爵家では、フランスの革命と国王の処刑に貴族は憤慨していた。クレールの再婚で男爵家の娘となっていたアデルは、落馬事故で母を亡くし義姉ロミーの幼馴染のヘッセン伯爵と婚約をしていた。ロミーの伯爵への愛に気づいてたアデルは、オランダと英国見物に行きたいと伯爵にせがみロミーと3人で出発する。英国にたどり着いたアデルはロミーに伯爵への想いを打ち明けるように諭し、一人レオンの待つフランスへ向かった。無事にフランスのたどり着いたアデルは貴族の逃し屋をやっていたリュウに出会い助けられる。貴族であるアデルは逮捕対象だった。
リュウと仲間のファーブルは、フランス革命の推移をアデルに語る。革命後の凶作の中で飢えた女たちは国王にパンをもらおうとヴェルサイユに行進を開始、男たちも続く。「パンがなければお菓子をたべればよい」という王妃マリー・アントワネットの言葉に激怒した民数は王と王妃をパリに連れ帰る。その後オーストリアに逃亡しようとした国王夫妻はヴァレンヌで捕らえられ幽閉され、その後ルイ16世は処刑される。それを聞いたアデルは「国民が信頼すべき王が逃げ出したのは国民への裏切りであり、処刑されたのは気の毒だが仕方がない」と答えた。アデルの回答を聞いた二人はアデルは只者ではないと悟るのだった。そして紛糾する議会において国王処刑のきかっけとなったのが「人間社会において王であるそのこと自体が罪であり、有罪、死刑」と発言したのがレオン(サン=ジュスト)であり「死の大天使」と呼ばれていると聞いたアデルは別人に違いないと考えた。
レオンに会うためにパリに向かったアデルだが馬車を乗り間違えたアデルはカーンでシャルロット・コルディーと出会った。(6巻中、1巻まで)、このあとアデル、レオン、リュウ3人の人生が交錯しながら物語が展開していく…..
『杖と翼』を読んでの感想
レオンは何の生きがいもなかった彼に生きるきっかけを与えてくれたクレールとアデル母娘に感謝をし、その勇気と聡明さを愛していた。そのため、貴族であり処刑の対象となるアデルを、身の危険を犯してまで何度も救っていく。彼がアデルに冷たくするのはアデルを気遣ってであり、革命家である自分には同士の妹である女性が相応しいと思っているからだった。アデルの事をいつも気にかけているのだが、それが愛だとは気が付かなかった。そしてアデルが死にかけて初めて彼女への愛に気づき、彼女が助かるならば何でも知ると神に祈る。確かにフランス革命史に残る「恐怖の大天使」かもしれないが、その革命への姿勢もアデルへの愛も崇高なものだ。
しかし、革命の理想を追求するままに反乱軍というだけで無力な女性や子供までも皆殺しにする「地獄の軍隊」の行動は行き過ぎた行動であり、因果応報となって跳ね返ってくることになった。聖女であるアデルに「さようなら」と言われたのは神に見捨てられたのと同義ということだろう。
アデルは「死の大天使」の評判を聞いても、彼の行動を見ても、その思想を否定しなかった。そのためレオンへの思慕の情は諦めるが、命をかけてまでレオンを助けた。しかし女性や子供にまで及ぶ「地獄の軍隊」の虐殺を知るとレオンを否定し、レオンとは異なる自らの力を使用した民衆への救済活動を開始する。レオンを怪物にしてしまった原因は自分にあると考え、レオンを止めようとするのだった。この時点からアデルの騎士はリュウのみとなり、レオンとアデルの道は違えることとなった。
『杖と翼』は、木原敏江作品の特徴である弱者の側から描かれた悲劇という側面も持つ。しかし、一方の主人公が救われることと、現在まで続く民主主義が築かれたのはこうした多くの犠牲があったからだと考えると、傷も癒やされる。
この解説に登場するのはアデル、レオン、リュウの3人のみだが、実はこの『杖と翼』には実在の人物を含め多くの魅力的なキャラクターが登場する。リュウの相棒のファーブル、その恋人のオランプ、アデルの弟のようなバランタンなどは架空の人物だが、皆非常に魅力的だ。実在の人物としてはフランス革命史に残るジャコバン派で最も人気のあったマラー、その暗殺者のシャルロット、日本では岩波ホールで上映されたドパルデュー主演伝記映画でも知られる雄弁で人情味のあるダントン、サン=ジュストの盟友であるロベスピエールなどだ。ジロンド党一派も含めこうした実在の人物の間のやり取りを見ても「革命はどうあるべきだったのか?」と考えさせられる。個人的には上記の映画の影響なのかダントンが魅力的に思えてしまう。
『杖と翼』に描かれているように、諸外国との戦争による重税や金持ちは身代わりを立てられる30万人の徴兵制により民衆を基盤とするジャコバン派が議会の主導権を握ってからも民衆の暮らしは楽にならなかった。カソリック国であるのに貧しい人を助けている善良な神父が教会ではなく議会への従属を拒否した場合には革命の敵とみなされた事実には非常に違和感がある。教科書では教えてくれないヴァンデの農民反乱などまで登場するのでフランス革命への理解が深まるだろう。
王党派の立場で書かれた『ベルばら』だけでなく民衆の立場から革命を描いたこの『杖と翼』を読んでから革命や王と王妃の死刑が正しかったかどうかを考えてみるべきではないだろうか?